タマゴよ、お前もか!消える養鶏農家

配合飼料価格の高騰、原油高、円安の影響で日本の食料産地が激しく揺さぶられています。とりわけ酪農、畜産への打撃は深刻で、厳しい赤字経営を迫られて農家の廃業や倒産が相次ぐ事態となってきています。これまで「物価の優等生」と称され、安定した供給と価格を維持してきた鶏卵も例外ではありません。2022年3月の巨大養鶏企業グループの倒産や高病原性鳥インフルエンザの感染拡大が鶏卵の生産基盤を大きく揺るがしています。今後、日本の養鶏はどうなるのか。鶏卵の生産はどうなっていくのかを元東京農業大学教授で、一般社団法人 日本養鶏協会エグゼクティブ アドバイザーの信岡誠治さんに聞きました。
コストは7割上昇 9割が赤字経営で経営難に直面する農家
―食料品や光熱費などの値上げを伝えるニュースが相次ぐなか、これまで「物価優等生」といわれてきた鶏卵の小売価格も見直され、2022年11月には前年同月比で1キロ当たり55円の引き上げとなりました。
背景には新型コロナウイルスの感染拡大とロシアによるウクライナへの軍事侵攻などの影響による原油高、円安、穀物価格の高騰があり、依然として先行きは不透明なままです。現在、日本の養鶏農家が直面している状況についてお聞かせください。
端的に言うと、いま日本の養鶏農家は「倒産・廃業の嵐」に見舞われています。昨年(2022年)11月に報道された55円の値上げ水準では、とても追いつかない状態にあるのです。というのも、鶏卵の生産コストの70パーセントは飼料代(採卵できるまでヒナを育成する期間の約150日を含む)です。残り20数パーセントがヒナ代などの資材費、設備や施設の償却費、燃料代、人件費などに費やされ、農家の純利益は配合飼料高騰前には数パーセントでしたが、現在は赤字という過酷な経営が常態化しつつあるからです。とりわけ飼料代と燃料代などが約2倍になり、コスト負担が6割から7割上昇したのに、その3割しか補てんできない値上げ幅です。これでは純益どころか赤字経営を余儀なくされて、今年2023年の初頭から経営の存続が困難になる養鶏農家が増えてくる可能性が高まってきました。
背景には新型コロナウイルスの感染拡大とロシアによるウクライナへの軍事侵攻などの影響による原油高、円安、穀物価格の高騰があり、依然として先行きは不透明なままです。現在、日本の養鶏農家が直面している状況についてお聞かせください。
端的に言うと、いま日本の養鶏農家は「倒産・廃業の嵐」に見舞われています。昨年(2022年)11月に報道された55円の値上げ水準では、とても追いつかない状態にあるのです。というのも、鶏卵の生産コストの70パーセントは飼料代(採卵できるまでヒナを育成する期間の約150日を含む)です。残り20数パーセントがヒナ代などの資材費、設備や施設の償却費、燃料代、人件費などに費やされ、農家の純利益は配合飼料高騰前には数パーセントでしたが、現在は赤字という過酷な経営が常態化しつつあるからです。とりわけ飼料代と燃料代などが約2倍になり、コスト負担が6割から7割上昇したのに、その3割しか補てんできない値上げ幅です。これでは純益どころか赤字経営を余儀なくされて、今年2023年の初頭から経営の存続が困難になる養鶏農家が増えてくる可能性が高まってきました。

1キロ55円の値上げといいますが、それはあくまでもJA全農たまご株式会社が発表したMサイズ1キロの基準価格です。鶏卵にはSS(40~46グラム未満)、S(46~52グラム未満)、MS(52~58グラム未満)、M(58~64グラム未満)、L(64~70グラム未満)、LL(70~76グラム未満)の規格があり、通常はMサイズの相場が最も高く、それ以外は若干安い価格で取引きされています。ですから今回の値上げ報道は「参考指標」としかいえないわけです。また、全農たまごに出荷される鶏卵は総生産量の15~16パーセントに過ぎず、それ以外の鶏卵は年間を通し、ほぼ一定価格で量販店などに納品されています。
「物価の優等生」といわれる鶏卵ですが、その安定した生産と価格を支えてきたのは技術革新です。とりわけ、この50年から60年は採卵鶏の産卵成績やブロイラーの増体成績、ワクチンによる病気の抑制、機械化を伴う規模拡大は飛躍的に進歩してきました。しかし、それによって1955年当時は451万戸あった養鶏農家が、わずか1810戸と2500分の1の水準まで激減しています。にもかかわらず、飼養羽数と生産量は増加し、安定した価格で1人年間約20キロの消費を賄ってきたのです。半世紀前は、養鶏農家が1000羽も飼育すれば暮らしていけたのに、現在は数万羽が当たり前となり、一戸当たり8万羽が平均的な飼養数になりました。これが「物価の優等生」を支える現実です。しかし、経営規模の拡大によって飼育羽数が増えれば飼料代や燃料代、資材費や設備費などの出費もかさみます。
いまでも千~数千羽を飼育する農家も少なくありません。それなのに飼養羽数の平均が8万羽という大きな数字になるのは、一つのグループで1300万羽を飼養する「ギガファーム(1000万羽以上)」と呼ばれる企業が存在するからです。日本では1000万羽以上の採卵鶏を飼養する企業は国内1社、それに続くのは1000万羽には達していませんが別の大手が1社、そして200~400万羽クラスの大手が10社程度で、これら10数社が鶏卵市場を押さえています。
巨大養鶏企業グループが倒産 鳥インフルの世界的流行が
―1グループで1300万羽を飼養する「ギガファーム」ですか。とはいえ、巨大化すればするほど生産コストは巨額になり、経営は厳しくなるのではありませんか。
飼料代はもちろん、防疫の衛生費、人件費がかさむのは当然ですし、飼料や鶏卵を搬入・搬出するための物流コストも膨大なものになります。それでも小売サイドからの要請に応え、通年で定価販売を続けるとなれば無理が生じるのは当然でしょう。2022年3月の倒産の真相はわかりませんが、そのグループ会社は国内のみならず中国や米国にも農場を展開し、インドや東南アジアにも支店を開設していましたが、負債総額は453億円とされ、会社更生の手続き策定の段階に入っています。銀行系ファンド、コンサルティング会社、国内の中堅養鶏事業者による再建計画が策定されているそうですが、まったく先行きは見通せません。問題はグループに所属していた養鶏会社の連鎖倒産です。農場が閉鎖されれば鶏の淘汰(とうた)が進み、鶏卵の国内生産の縮小につながる恐れがあります。たとえ、グループ企業の再建がなされたとしても、その過程で飼育条件や出荷のための物流条件が良くない農場は放棄され、やはり鶏の淘汰が進むはずです。これまでは資本力に裏打ちされたギガファームなら、多少の生産コストの上昇には耐えられとされてきましたが、そんな「経済通念」が崩れたといっていいかと思います。
日本での卵の流通は、半分は「テーブルエッグ」と呼ばれるパックに入ったパック卵、あと半分が「業務用」として流通しています。業務用は10キロ入りのダンボール、あるいはプラスチックのコンテナ入りで流通している卵です。業務用の卵の多くは「加工卵」として飲食店やパン製造事業者に利用されています。
そのパック卵の流通を先導し年間定価で出荷販売してきた巨大養鶏企業グループが倒産したのですから、その影響は今後本格化してくるとみられます。
こうしたなか、堅実な養鶏経営を続けているのは中小規模の養鶏農家です。彼らは生活協同組合と提携したり、自前の販売ルートを確保したりしながら、飼料用米を活用するなどして生産コストを下げながら、厳しい経営環境を乗り越えようとしています。とはいえ、彼らの努力を水疱(すいほう)に帰してしまいかねない世界的な大きな問題があります。それは「種」の独占と「高病原性鳥インフルエンザ」の世界的な感染拡大です。
飼料代はもちろん、防疫の衛生費、人件費がかさむのは当然ですし、飼料や鶏卵を搬入・搬出するための物流コストも膨大なものになります。それでも小売サイドからの要請に応え、通年で定価販売を続けるとなれば無理が生じるのは当然でしょう。2022年3月の倒産の真相はわかりませんが、そのグループ会社は国内のみならず中国や米国にも農場を展開し、インドや東南アジアにも支店を開設していましたが、負債総額は453億円とされ、会社更生の手続き策定の段階に入っています。銀行系ファンド、コンサルティング会社、国内の中堅養鶏事業者による再建計画が策定されているそうですが、まったく先行きは見通せません。問題はグループに所属していた養鶏会社の連鎖倒産です。農場が閉鎖されれば鶏の淘汰(とうた)が進み、鶏卵の国内生産の縮小につながる恐れがあります。たとえ、グループ企業の再建がなされたとしても、その過程で飼育条件や出荷のための物流条件が良くない農場は放棄され、やはり鶏の淘汰が進むはずです。これまでは資本力に裏打ちされたギガファームなら、多少の生産コストの上昇には耐えられとされてきましたが、そんな「経済通念」が崩れたといっていいかと思います。
日本での卵の流通は、半分は「テーブルエッグ」と呼ばれるパックに入ったパック卵、あと半分が「業務用」として流通しています。業務用は10キロ入りのダンボール、あるいはプラスチックのコンテナ入りで流通している卵です。業務用の卵の多くは「加工卵」として飲食店やパン製造事業者に利用されています。
そのパック卵の流通を先導し年間定価で出荷販売してきた巨大養鶏企業グループが倒産したのですから、その影響は今後本格化してくるとみられます。
こうしたなか、堅実な養鶏経営を続けているのは中小規模の養鶏農家です。彼らは生活協同組合と提携したり、自前の販売ルートを確保したりしながら、飼料用米を活用するなどして生産コストを下げながら、厳しい経営環境を乗り越えようとしています。とはいえ、彼らの努力を水疱(すいほう)に帰してしまいかねない世界的な大きな問題があります。それは「種」の独占と「高病原性鳥インフルエンザ」の世界的な感染拡大です。

採卵鶏のヒナを手に入れるにはエリートストック(ES)という優秀な純粋種を元に原原種鶏(GGP=グレートグランドペアレント=曾祖父母)を作出し、その交配を重ね、原種鶏(GP=グランドペアレント=祖父母)を得て、それらを交配して種鶏(P=ペアレント=親)を増殖し、さらに種鶏を交配させて実用鶏(CM=コマーシャル=採卵鶏)のヒナを作出するというプロセスを経る必要があります。それには大元の純粋種のエリート鶏やGGPを保有していなければなりませんが、この「種」を握っているのは現在、世界で2社しかありません。ドイツのEWグループ(イーダブリュー・グループ)とオランダのHG(ヘンドリックス・ジェネティックス)社だけです。
現在は、EWグループが販売する種鶏が世界市場を席巻していて、ほぼ独占状態にあります。ヨーロッパ、アフリカ、中国、日本、米国、南米諸国も「種」の供給は同社に依存せざるを得なくなっています。いま全世界に流通している種鶏の販売羽数は約2000万羽です。ヒナ1羽当たりの世界の平均価格は500円ほどです。日本への販売価格はその2倍以上といいますから、最高値で買わされていることになります。EWグループの生産拠点は米国にもヨーロッパにもあり、そこからGGP、GPを卵やヒナの状態で日本は輸入しています。それらを日本で増殖して、コマーシャル鶏(採卵鶏)を作っているわけです。ヒナは1羽100円程度ですが、それを育成し卵を産むまでには約150日間かかります。すぐに採卵が可能な大ビナ(若メス)は120日齢で1羽が1000円程度です。
こうした世界の動きに流されまいと頑張っているのが、岐阜県にある後藤孵卵場です。唯一の国産鶏として存在するのが後藤孵卵場の「もみじ」と「さくら」です。この二つの鶏種は生活クラブ生協をはじめとする生協陣営の共同購入で支えられていますが、これは大事な取り組みだと思います。
鶏の「種」がほぼ独占状態にあるからといって、すぐにヒナが輸入できなくなるはずがないという声があります。すぐに「有事」を持ち出して、いたずらに不安をかき立てるなという人もいるでしょう。そうかもしれません。しかし、安閑としてはいられない現実があります。新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)さながらに、鳥インフルエンザウイルスが世界的な感染拡大の様相を呈しています。EWグループもHG社も「種」の保全のための防疫体制を強化し、感染リスクの分散を目的として世界各地に農場を分散していますが、ウイルスという自然の驚異に対抗できる「絶対の安全確保」は残念ながら不可能というしかありません。すでにヨーロッパでは鳥インフルエンザに感染した鶏が5000万羽以上も殺処分され、米国でも5000万羽以上が殺処分されています。

そんな危機的状況のなか、世界各国の研究機関や大学ではワクチン開発や遺伝子組み換えやゲノム編集技術を駆使して、鳥インフルエンザに強い鶏の開発に力を入れています。ワクチンに絶対的な効果があるわけではないのは、新型コロナウイルスへのワクチン接種を見ても明らかでしょう。鶏にも備蓄した鶏インフルエンザワクチンがありますが、現在ワクチン接種は認められていません。ワクチンを接種しても感染は防げない陽性鶏になるなど、効果的な防疫法がないのが実情なのです。すでに欧米では白鳥にカモやアヒルなど、野鳥の4割近くが陽性鳥であるとの情報があります。感染拡大の原因はエアロゾル感染ではないかとされています。空気中のほこりや羽毛に鳥インフルエンザウイルスが付着して、感染拡大しているのではないかということです。ウインドレス鶏舎で出入りする人は完全に消毒を行い、外部から鳥類だけでなくネズミなどの小動物の侵入を完全に遮断していても感染するわけですから、どんなに衛生管理に努力をしても完璧な防御は困難です。日本で79年ぶりに鳥インフルエンザが発生したのは2004年でしたが、以後18年間でウイルスの毒性と感染力がより強くなっているとの報告もあります。
このままでは「産業崩壊」それでも政府は見て見ぬふり?
―このままの状態が続くと、日本の採卵養鶏はどうなってしまうのでしょうか。
冗談ではなく養鶏産業崩壊の恐れが出てきました。最悪の場合でも、鶏の場合はライフサイクルが早いため、1~2年のスパンで回復できる可能性は残されています。ただし「エリートストック」や「原原種」が保存されていなければいかんともしがたいわけです。だからEWグループやHG社は原原種を飼養している農場の場所を完全に秘匿していますし、徹底的なリスク分散策を講じてもいます。
同様に日本では後藤孵卵場が国内で原原種の保存に大きなコストと手間をかけて努めています。まさに希望の星といえるでしょう。
冗談ではなく養鶏産業崩壊の恐れが出てきました。最悪の場合でも、鶏の場合はライフサイクルが早いため、1~2年のスパンで回復できる可能性は残されています。ただし「エリートストック」や「原原種」が保存されていなければいかんともしがたいわけです。だからEWグループやHG社は原原種を飼養している農場の場所を完全に秘匿していますし、徹底的なリスク分散策を講じてもいます。
同様に日本では後藤孵卵場が国内で原原種の保存に大きなコストと手間をかけて努めています。まさに希望の星といえるでしょう。

それにしても自然(ウイルス)の脅威はすさまじいものです。完全密閉式のウインドレス鶏舎でも、鳥インフルエンザウイルスの侵入を完全に防ぎ止めることは不可能な状況です。もはやアニマル・ウェルフェアの考えに立った放し飼いは不可能な状況になってきました。
そればかりか、近い将来にはゲノム編集によって開発された鶏が世界的に流通するようになるでしょう。ゲノム編集は遺伝子を操作した痕跡を科学的に追跡するのが困難とされており、そうではない鶏との区別ができない特性を持っています。しかし、それ以外に選択肢がなくなるとしたら、何が「絶対的安全」なのか、「100パーセントの安全」があるのかという厳しい問いに対し、私たち消費者は結論を出さざるを得なくなるでしょう。しかし、差し迫った当面の課題は中小の養鶏農家の廃業・倒産をいかに防ぐかです。
55円値上げして1キロ平均262円ではどうにもなりません。すでに米国では1キロ400円が当たり前になりつつあります。そうしなければ生産基盤が守れず、消費者の不利益にもつながるからです。ところが、日本の政府は養鶏業界の苦境を見て見ぬふりをしているかのように動きが鈍いのです。養鶏場の周囲に消毒薬を散布して感染を防ぐことを緊急対策として実施してはいますが、効果は疑問というしかないのが現状です。また、飼料価格の暴騰に対応した機動力のある抜本的な助成措置や経営救済策を講じようとはしていません。
おまけに飼料用米を栽培する面積が増え、財政負担が重くなったとして助成金の支出額を減らす方向で動いています。これで「食料安全保障」が追求できるのかと、あまりの国家戦略の無さに唖然(あぜん)とするばかりです。
日本の鶏卵の自給率は96パーセントとされていますが、飼料を輸入依存しているため、実際は13パーセントほどに下がるという話は良く耳にすると思います。しかし、たとえ飼料がこれまで通り輸入できたとしても卵の自給率は80パーセントしかないのが本当の姿だろうと見ています。
というのも、貿易統計では卵の輸入量にはカウントされない“卵調製品”の輸入が実は相当な規模で存在するからです。中国から輸入している総菜や加工品などは膨大な種類と量があります。それらには鶏卵がほとんどの場合使われていて、卵の配合率は数パーセントから数10パーセントと様々ですが、積み上げていくとこれがばく大な量になってきます。だれも正確に把握できていませんが、ギョーザの皮、点心をはじめ、ありとあらゆるものに入っているのです。この隠れ輸 入卵である卵調製品の輸入も、いつ止まるかわからないものです。
日本国内の鶏卵の生産基盤が文字通り「累卵の危機」に瀕している現状を考えれば、やはり鶏卵は実に貴重な国産品であると再認識する必要があるのは間違いないと思います。
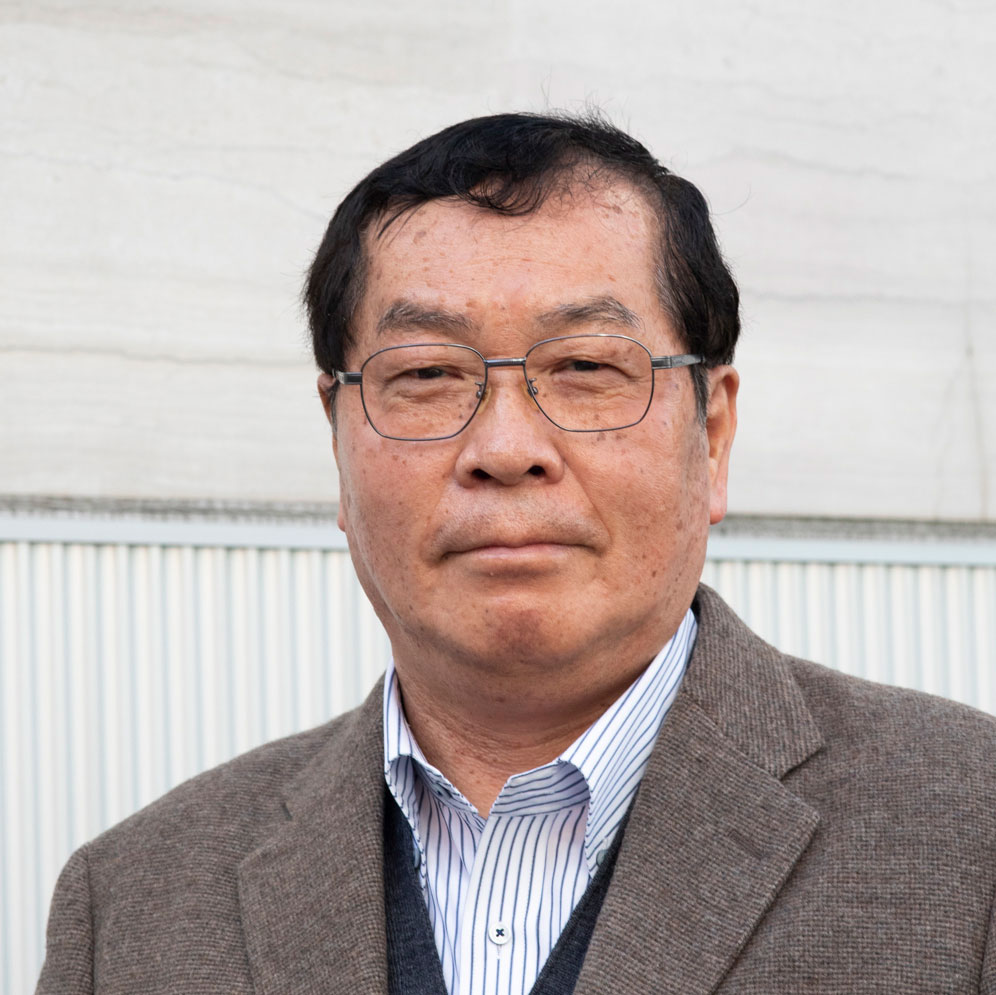
のぶおか・せいじ
1952年広島県生まれ。日本獣医生命科学大学卒、岐阜大学大学院農学研究科修士課程修了。全国農業会議所入会、全国農業新聞編集部で農村現場の取材、全国農業会議所調査部で農地価格、小作料、農作業料金などの調査事業に従事する。2006年に東京農業大学に移り、農学部畜産学科教授を経て2018年定年退職。現在、飼料用米振興協会、日本養鶏協会の事業に参画。飼料米の生産から給与まで一貫した試験研究や飼料米給与畜産物のマーケティング研究に力を注ぐ。主な著書に「資源循環型畜産の展開条件」(農林統計協会)、「畜産学入門」(文永堂出版)、「我が国における食料自給率向上への提言PART-2、PART-3」(筑波書房)などがある。
撮影/魚本勝之
取材構成/生活クラブ連合会 山田衛




