生産者と消費者で守る エビ本来の味

弾力ある身としっかりしたうまみの「エコシュリンプ」は、一度食べれば一般の冷凍エビとの違いがわかる逸品だ。おいしさだけではない。その名に「エコ」と付く通り、環境に配慮した持続可能な養殖方法や生産者とともに食の安全性を追求する姿勢を支持する組合員も多い。だが、近年、生産現場のインドネシアに気候変動の波が押し寄せている。生産者の生活と養殖池の自然環境を守るため、現地ではさまざまな取り組みが行われている。

調理例の「ガーリックシュリンプ」。「エコシュリンプ」をおいしく食べるには、調理の直前に流水解凍するのが一番。冷蔵庫で一晩かけて解凍すると、ドリップでうまみが抜けてしまう
「民衆交易」とは何か
生産者と消費者が相互に支え合う関係で取引する「民衆交易」を掲げ、「エコシュリンプ」を輸入・販売しているのが、提携先のオルター・トレード・ジャパン(以下、ATJ)だ。その歴史をひもとくと、「民衆交易」の理念が見えてくる。
1980年代半ば、砂糖の国際価格が暴落すると、サトウキビ産業に依存していたフィリピン、ネグロス島の農園労働者たちが飢餓に陥った。86年、彼らを支援すべく発足した市民団体「日本ネグロス・キャンペーン委員会(以下、JCNC)」は、翌87年に「マスコバド糖」(精製を一切しないミネラル分豊かな砂糖)の輸入・販売を開始する。飢餓の救済キャンペーンとして始まったこの活動は、その後、現地の人々の経済的自立を目指した「産直活動」へと発展していく。
89年2月、JCNCは「1日3回の食事がしたい」「子どもを高校に行かせたい」というネグロス島の人々の願いと、「子どもが安心して食べられるバナナを」という日本の消費者の願いをかなえるため、化学合成農薬不使用で栽培した在来品種「バランゴンバナナ」の試験輸入を開始した。バナナを適切な価格で継続的に共同購入すれば、生産者の経済的自立につながるとともに、日本の人々が、安全なバナナを食べられるようになる。
1980年代半ば、砂糖の国際価格が暴落すると、サトウキビ産業に依存していたフィリピン、ネグロス島の農園労働者たちが飢餓に陥った。86年、彼らを支援すべく発足した市民団体「日本ネグロス・キャンペーン委員会(以下、JCNC)」は、翌87年に「マスコバド糖」(精製を一切しないミネラル分豊かな砂糖)の輸入・販売を開始する。飢餓の救済キャンペーンとして始まったこの活動は、その後、現地の人々の経済的自立を目指した「産直活動」へと発展していく。
89年2月、JCNCは「1日3回の食事がしたい」「子どもを高校に行かせたい」というネグロス島の人々の願いと、「子どもが安心して食べられるバナナを」という日本の消費者の願いをかなえるため、化学合成農薬不使用で栽培した在来品種「バランゴンバナナ」の試験輸入を開始した。バナナを適切な価格で継続的に共同購入すれば、生産者の経済的自立につながるとともに、日本の人々が、安全なバナナを食べられるようになる。
「安定的に提携して、生産者と消費者双方の利益を追求しつつ、環境に配慮した安全な方法で生産した食べ物を、公正な価格で交易する」――こうした「民衆交易」を確立するため、89年10月には、各生協や市民団体、個人などの出資を受けて、ATJが設立された。生活クラブ連合会も当初から出資し、「バランゴンバナナ」の輸入が本格化すると、共同購入も定着していった。
ATJの代表取締役社長、山下万里子さんは、こう説明する。
「『民衆交易』では、生産者の事情に寄り添って関係を築いていきます。また、生産者と消費者の交流会を開いて、顔の見える関係を築いていくのも『民衆交易』の大切な仕事です」
ATJの代表取締役社長、山下万里子さんは、こう説明する。
「『民衆交易』では、生産者の事情に寄り添って関係を築いていきます。また、生産者と消費者の交流会を開いて、顔の見える関係を築いていくのも『民衆交易』の大切な仕事です」
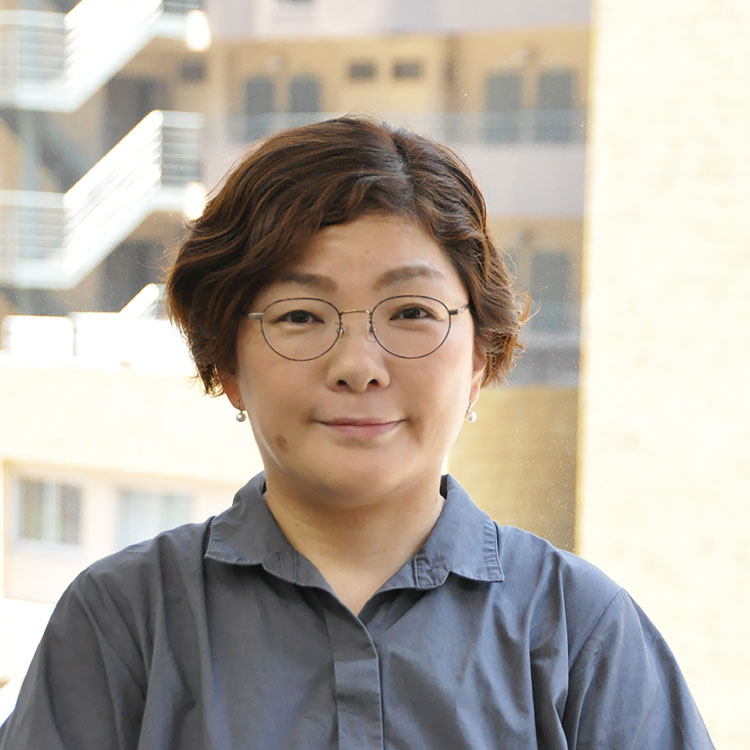
株式会社オルター・トレード・ジャパン代表取締役社長、山下万里子さん(撮影:本紙・山本 塁)
のびのび育てる「粗放(そほう)養殖」

インドネシアの地図。赤字が「エコシュリンプ」の産地(オルター・トレード・ジャパン提供の地図に一部加筆)
92年、ATJが始めたのが、「エコシュリンプ」の「民衆交易」だった。当時、日本はバブル景気を経てエビの需要が拡大し、世界一のエビ消費国になっていた。そのほとんどを輸入に依存していたことから、天然エビの枯渇が懸念される一方で、人工飼料や抗生物質を与えた養殖の冷凍エビが大量に日本に輸入されるようになる。養殖エビの産地では、大量生産に適した集約型養殖が盛んになり、コンクリート製の養殖池が次々に建設された。そのため、マングローブの伐採が進むなど、環境破壊も起きた。
こうした時代背景により、組合員をはじめとする消費者から、環境に配慮した、安心・安全なエビを食べたいという声が上がる。この要望に応えるため、ATJは、自然な環境でエビを養殖している産地を探した。そこで出会ったのが、インドネシアのエビの生産者たちだった。
「ジャワ島のグレシックは300年を超える魚の養殖の歴史があり、しかも時代のニーズに合わせてエビの養殖も始めていたんです」と山下さんは言う。その後、安定供給のために、ジャワ島のシドアルジョおよびスラウェシ島のピンランの生産者とも契約し、「民衆交易」の輪は広がっていった。
「エコシュリンプ」は、ブラックタイガーという品種のエビを「粗放養殖」という方法で育てている。水草を繁茂させた養殖池に稚エビを放流し、人工飼料や抗生物質は使わずに、プランクトンなどの天然の餌で育てるのが特徴だ。池の中のエビの密度は、1平方メートル当たり3~4匹程度で、これは集約型養殖の10分の1程度だ。ブラックタイガーは、餌を求めて池の底を自由に動きまわるので、身が引き締まった筋肉質のエビに育つ。人工飼料や抗生物質を使わずにきちんと養殖されているかどうかは、現地法人であるオルター・トレード・インドネシア(以下、ATINA)の監査員が毎日のように生産者を訪ねまわり、細かくチェックして品質管理に務めている。

スラウェシ島のピンランでは、定置網を張ってエビを収獲している

ジャワ島のシドアルジョでは、「プラヤン」という竹かごでエビを収獲する。収獲方法はいろいろで手づかみの生産者もいる

海岸沿いの汽水域に広がるスラウェシ島ピンランの養殖池。海面上昇により、この海岸が浸食に脅かされている

バナメイエビの需要増におされ、ブラックタイガーの稚エビの生産量が減り、放流に適したサイズが入手困難になっている。稚エビの養育場で約十日間、大きく育ててから放流する方法に変え、生存率を上げる取り組みをしている
「産地1回バラ凍結」の効果

目視と触覚で異物が混入していないか確認する作業風景。頭部除去などの下処理もすべて手作業だ。除去した頭部は「海老のクリームパスタソース」や「海老のビスクスープ」に加工して販売している
稚エビの放流から3~4カ月で収獲となるが、ここから先はいかに鮮度よく「エコシュリンプ」を消費者に届けるかにかかっている。収獲したらすぐに氷が詰まったクーラーボックスに入れ、品温4度以下を維持したまま工場に運ぶ。洗浄後に頭部除去、背ワタ取りなどの下処理をしたあとは、1尾ごとにバラで凍結する。次に冷凍したエビを一度水にくぐらせ、表面に薄い氷の膜を張る。この「グレージング」という工程によって、エビは氷の膜に守られるので、空気に触れなくなり、冷凍焼けによる身の乾燥を防げる。その後、「エコシュリンプ」は一度も解凍されることなく、組合員のもとへ届けられる。この「産地1回バラ凍結」が「粗放養殖」と並んで「エコシュリンプ」のおいしさの秘密だと山下さんは言う。
「スーパーで冷凍エビを見ていただくと、『加工所』が記載されている商品があると思います。こうした商品は、板状の氷にエビを閉じ込めた状態で輸入され、それを国内の加工所で解凍して小分けにし、再冷凍したものなんです。一度解凍すると、うまみが流出し、食感が損なわれてしまいますから、人工的にエビのプリプリ感を出すために保水剤を投与したり、変色を防ぐために黒変防止剤を投与したりしているケースが多いです。その点、『エコシュリンプ』は、『産地1回バラ凍結』ですから、薬剤を使用せずに、エビ本来のおいしさを維持できます」
「スーパーで冷凍エビを見ていただくと、『加工所』が記載されている商品があると思います。こうした商品は、板状の氷にエビを閉じ込めた状態で輸入され、それを国内の加工所で解凍して小分けにし、再冷凍したものなんです。一度解凍すると、うまみが流出し、食感が損なわれてしまいますから、人工的にエビのプリプリ感を出すために保水剤を投与したり、変色を防ぐために黒変防止剤を投与したりしているケースが多いです。その点、『エコシュリンプ』は、『産地1回バラ凍結』ですから、薬剤を使用せずに、エビ本来のおいしさを維持できます」

一尾ごとにバラ凍結されたエビ
養殖池を襲う豪雨と海面上昇
そんな「エコシュリンプ」の生産者たちを苦しめているのが、異常気象だ。ブラックタイガーは、海水と淡水が混じった汽水域(きすいいき)で育てるが、度重なる豪雨で養殖池の塩分濃度が下がってしまい、エビが死んでしまう事態が起きている。
「晴れ続きで塩分濃度が上がれば淡水を引き入れ、雨で塩分濃度が下がれば海水を引き入れて、塩分濃度を調整します。ところが、あまりの豪雨で池が氾濫してしまうと、打つ手がありません」
そのうえ近年は、乾季と雨季の境目がなくなってしまったと山下さんは嘆く。
「乾季の間に池の水を抜いて日に干し、石灰をまいて土壌を整えるのですが、乾季、雨季に関係なく大雨が降るようになってしまったため、池干しできない生産者が増えています。また、海面上昇による海岸浸食も進んでいて、過去5年間に最大で50メートル内陸にある養殖池が海に沈んでしまったところがあります」
対策として、生産者とATINAが立ち上げた環境NGO「PANDU(パンドゥ)」は、沿岸地域にマングローブを植える活動をしている。マングローブの根が張ると、養殖池の土手がしっかりして、海岸浸食を食い止める効果があるからだ。産地の自然や働く人の環境に思いを寄せ、生産者とともにこれらを守る活動に取り組む――これもまた、「民衆交易」の大切なひとつの形だ。
「晴れ続きで塩分濃度が上がれば淡水を引き入れ、雨で塩分濃度が下がれば海水を引き入れて、塩分濃度を調整します。ところが、あまりの豪雨で池が氾濫してしまうと、打つ手がありません」
そのうえ近年は、乾季と雨季の境目がなくなってしまったと山下さんは嘆く。
「乾季の間に池の水を抜いて日に干し、石灰をまいて土壌を整えるのですが、乾季、雨季に関係なく大雨が降るようになってしまったため、池干しできない生産者が増えています。また、海面上昇による海岸浸食も進んでいて、過去5年間に最大で50メートル内陸にある養殖池が海に沈んでしまったところがあります」
対策として、生産者とATINAが立ち上げた環境NGO「PANDU(パンドゥ)」は、沿岸地域にマングローブを植える活動をしている。マングローブの根が張ると、養殖池の土手がしっかりして、海岸浸食を食い止める効果があるからだ。産地の自然や働く人の環境に思いを寄せ、生産者とともにこれらを守る活動に取り組む――これもまた、「民衆交易」の大切なひとつの形だ。

このように水を抜いて池を干した後は、石灰をまいて土壌を中和させ、耕す。水を張って水草を繁茂させ、エビが育ちやすい環境を整える

PANDUによるマングローブの植林風景

インドネシアにはごみ収集の仕組みが整っていない場所が多く、環境汚染が問題になっている。産地では「粗放養殖」の環境を維持するため、家庭ごみ収集の活動に取り組み、自治体にも働きかけている
写真提供/オルター・トレード・ジャパン
文/本紙・山本 塁
『生活と自治』2024年10月号「連載 ものづくり最前線 いま、生産者は」を転載しました。
【2024年10月20日掲載】




