伊勢の海と人の知恵が作る、香り高いのり
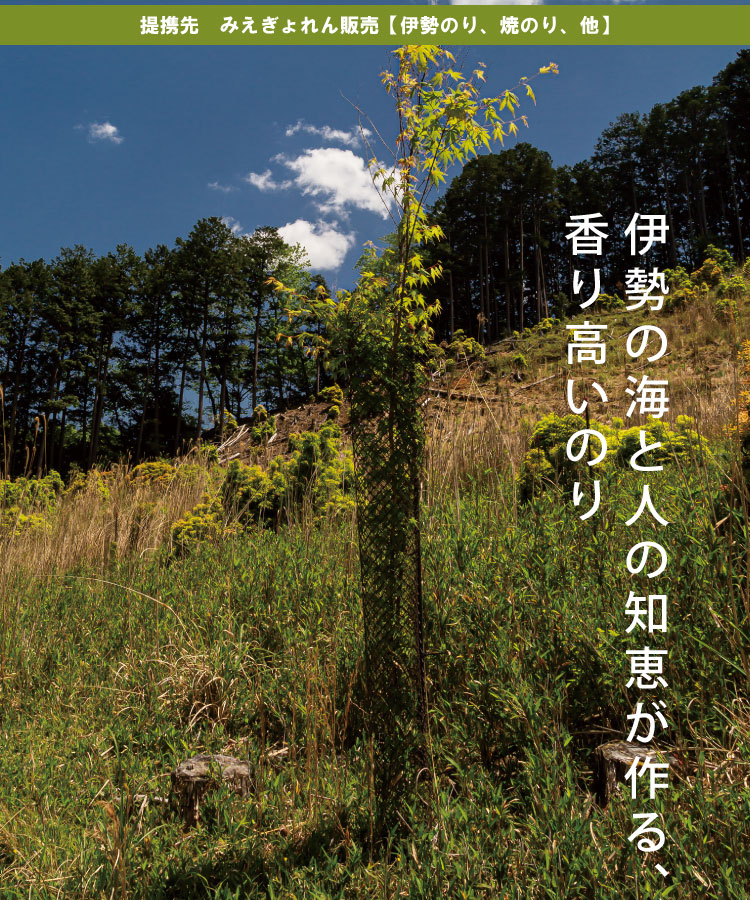
みえぎょれん販売株式会社(以下、みえぎょれん販売)は、三重県鳥羽市の漁師たちが養殖、加工製造したのりを、生活クラブ連合会向けに厳選し、「伊勢のり」「焼のり」として供給する。ノリ養殖にとっては厳しい気候環境が続く中、新しい挑戦を試みる漁師を支える一方で、栄養豊かな海の環境を守るため、三重県漁業協同組合連合会(以下、三重県漁連)が推進する「森と海をつなぐ運動」にも参加する。
海水温に敏感なノリ
おにぎりやのり巻きに欠かせないのりは、和名をスサビノリという海藻を原料に、古くから確立している養殖技術により作られる。網にタネ(胞子)をつけ発芽させ、海水温が下がる秋に海に出し、冬の間に成長したノリを収穫し、紙のように漉(す)き乾燥したものが板のりだ。
生活クラブ連合会の提携生産者、みえぎょれん販売が提供する伊勢のりの原料ノリは、三重県鳥羽市の鳥羽磯部漁業協同組合(以下、鳥羽磯部漁協)の養殖場で生産される。鳥羽市沖の答志島(とうしじま)の桃取町(ももとりちょう)と答志町、菅島(すがしま)と、鳥羽港近くの安楽島(あらしま)町にあり、これらがある伊勢湾には木曽川や長良川が注ぎ、紀伊半島の山々を水源とする一級河川が山の栄養を運び流れ込む。さらに答志島近辺は伊勢湾と太平洋が接し、三重県ではノリの生育に適した有数の養殖場になっている。
しかし、桃取町の漁師、前田祥太さんは、このごろ海の様子や養殖ノリの生育状況が変わってきたと言う。「海水温が高くなり、ノリの漁期が短くなりました。ノリが成長する適温は18度ですが、秋になってもなかなか海水温が下がりません」。
生活クラブ連合会の提携生産者、みえぎょれん販売が提供する伊勢のりの原料ノリは、三重県鳥羽市の鳥羽磯部漁業協同組合(以下、鳥羽磯部漁協)の養殖場で生産される。鳥羽市沖の答志島(とうしじま)の桃取町(ももとりちょう)と答志町、菅島(すがしま)と、鳥羽港近くの安楽島(あらしま)町にあり、これらがある伊勢湾には木曽川や長良川が注ぎ、紀伊半島の山々を水源とする一級河川が山の栄養を運び流れ込む。さらに答志島近辺は伊勢湾と太平洋が接し、三重県ではノリの生育に適した有数の養殖場になっている。
しかし、桃取町の漁師、前田祥太さんは、このごろ海の様子や養殖ノリの生育状況が変わってきたと言う。「海水温が高くなり、ノリの漁期が短くなりました。ノリが成長する適温は18度ですが、秋になってもなかなか海水温が下がりません」。
鳥羽磯部漁協の桃取町支所長、中村英樹さんは、「20年以上前は、11月に入るとノリは大きく成長して収穫できましたが、今は12月中旬にならないと収穫できません。ノリ漁が終わるのは以前と変わらず翌年の3月なので、漁期にとれる量が1カ月分少ないのです」。この3年間の漁期が特に短かったと言う。
桃取町では、「浮き流し養殖」といって、ノリのタネを網につけていかだに張り、海面に浮かべる方法で養殖を行う。タネはカキ殻の中で増え、海水温が23度以下になると海水中に放出される。これを網につけるのがタネつけで、「経験が必要で、ノリの収量がほぼ決まる一番大事な作業です」と前田さん。9月20日過ぎからタネつけをするのが習慣で、以前はこの作業を海上で行っていた。年々海水温が上がり、現在はこの時期に海上ではできなくなり、陸上の水槽でカキ殻を冷やしながら行う。
タネつけをした網は一旦冷凍保管する。海水温が23度まで下がったら沖に出して芽を育て、芽がついた網を再び冷凍保管し海水温が18度に下がるまで待つ。
桃取町では、「浮き流し養殖」といって、ノリのタネを網につけていかだに張り、海面に浮かべる方法で養殖を行う。タネはカキ殻の中で増え、海水温が23度以下になると海水中に放出される。これを網につけるのがタネつけで、「経験が必要で、ノリの収量がほぼ決まる一番大事な作業です」と前田さん。9月20日過ぎからタネつけをするのが習慣で、以前はこの作業を海上で行っていた。年々海水温が上がり、現在はこの時期に海上ではできなくなり、陸上の水槽でカキ殻を冷やしながら行う。
タネつけをした網は一旦冷凍保管する。海水温が23度まで下がったら沖に出して芽を育て、芽がついた網を再び冷凍保管し海水温が18度に下がるまで待つ。

鳥羽磯部漁業協同組合桃取町支所長の中村英樹さん。「答志島近辺は風が強いです。ノリ漁に出られる日は集中して収穫し、冷凍保管します」

ノリ養殖用の網を巻きつけて回転させ、水槽に漬けながらノリのタネつけをする道具

ノリ漁の漁船。養殖網をすくい上げる独特の設備が備えられている
秋芽ノリに挑戦
現在は漁期の冬に網を1回張る1期作が主流だ。今ほど海水温が高くなかった頃、桃取町では秋芽ノリといって、秋口に網を張り11月にノリを収穫し、その後、冷凍しておいた網を張り替えてもう1回ノリを栽培する2期作が行われていた。
前田さんたち漁師は2期作を復活させようと「鳥羽地区黒のり養殖研究協議会」が中心となって、品種改良を重ねながら、3年前より秋芽ノリの栽培に取り組んでいる。「通常のノリは11月に20度を切ったぐらいで網を張りますが、秋芽ノリはそこまで下がらないうちに網を出します」。1年目は小規模だがうまくいった。2年目は予定の2~3割しかとれず、色も薄いものになり失敗だった。今回は予想以上の収穫があった。
「今のところ失敗の原因はわかりません。これからも続けたいので、データをとりながら、どうしたら失敗をできるだけ抑えられるかと常に考えています」と前田さん。養殖は自然の中で営まれる仕事だ。自然環境は毎年変わり、その中でさまざまな要因によりノリの収量が決まっていく。「今は海水温が高く、黒潮が蛇行しています。温暖化がすすんでいるなどと言われていますが、自分が生きている年月は、地球の何億年という歴史の中の一コマにすぎません。たまたまこういう条件の時期にこの仕事をしているだけです。大打撃ですけど」と笑いながら、ノリ養殖で暮らしていく覚悟だと言う。
「今のところ失敗の原因はわかりません。これからも続けたいので、データをとりながら、どうしたら失敗をできるだけ抑えられるかと常に考えています」と前田さん。養殖は自然の中で営まれる仕事だ。自然環境は毎年変わり、その中でさまざまな要因によりノリの収量が決まっていく。「今は海水温が高く、黒潮が蛇行しています。温暖化がすすんでいるなどと言われていますが、自分が生きている年月は、地球の何億年という歴史の中の一コマにすぎません。たまたまこういう条件の時期にこの仕事をしているだけです。大打撃ですけど」と笑いながら、ノリ養殖で暮らしていく覚悟だと言う。

答志島桃取町の漁師、前田祥太さん
森をつくる運動も

三重県津市美杉町にある「三重漁民の森」。伊勢湾に注ぐ雲出川(くもずがわ)河口から20キロメートルほどさかのぼったところにある
「ノリ漁師は、環境が変わり従来の養殖では思うような収穫が得られなくても、あきらめないで自分たちでできることを考えて行動に移しています」と、みえぎょれん販売の営業部長、前田昌範さん。みえぎょれん販売は、三重県の水産研究所などで試行されている秋芽ノリに適した品種の改良に協力するとともに、三重県漁連が「森と海をつなぐ運動」の一つとして1998年より続けている「三重漁民の森」の植樹に参加、海の環境維持に取り組む。
日本の高度経済成長期以降、川が運ぶ生活排水や工業排水により養殖業などの漁業が打撃を受けた。排水規制など対策がとられ、せっけん運動も広がる一方、漁師は山の広葉樹の落ち葉が腐葉土になり、たくわえられた養分が川によって海へ運ばれることを知り、山に木を植える活動を始めた。その運動は90年頃から全国に広がり、三重県でも「森と海をつなぐ運動」として展開されている。
今年3月、津市美杉町で三重漁民の森の植樹が行われた。標高約170メートルのスギ伐採地で、地域の漁協や環境保全活動に取り組む団体などから129人が参加し、イロハモミジやヤマザクラなど44本を植えた。生活クラブ愛知の組合員10人も急斜面での植樹を体験した。
「木を植えたからといってすぐに効果が表れるわけではありませんが、山の栄養が川によって海に運ばれ、海の生物が暮らす豊かな環境をつくっている、といったことを実感できたと思っています」とみえぎょれん販売の前田さん。自分たちができることを地道にコツコツと続けていくと言う。
今年3月、津市美杉町で三重漁民の森の植樹が行われた。標高約170メートルのスギ伐採地で、地域の漁協や環境保全活動に取り組む団体などから129人が参加し、イロハモミジやヤマザクラなど44本を植えた。生活クラブ愛知の組合員10人も急斜面での植樹を体験した。
「木を植えたからといってすぐに効果が表れるわけではありませんが、山の栄養が川によって海に運ばれ、海の生物が暮らす豊かな環境をつくっている、といったことを実感できたと思っています」とみえぎょれん販売の前田さん。自分たちができることを地道にコツコツと続けていくと言う。

みえぎょれん販売株式会社営業部長の前田昌範さん。「伊勢のりを、ぜひ焼いて食べてください」
焼き立てののりを

桃取町の若き漁師。左より、斎藤誠也さん、前田祥太さん、清水剛幸さん
ノリの収穫は厳寒期の仕事だ。朝早く船を出しノリを摘む。以前は、漁師が持つ加工場でノリを洗い刻み、枠に流して乾燥させ、板のりに仕上げるまでの全工程を個々に行っていた。その作業は夜中まで続いたという。
鳥羽磯部漁協はこの状況を打開し漁師の作業の軽減を図ろうと、10年前に答志町に共同加工場を設け、収穫したノリの加工を専門の職人に委託するようにした。その後菅島にも設けられ、桃取町でも5年前より稼働が始まった。労働環境改善に一定の成果はあったものの、後継者を増やそうとの目的に反し、最盛期には70軒だった桃取地区のノリ養殖漁師は7軒にまで減ってしまう。船上作業の過酷さは変わらず、気温の変化により不作の年が続いたこともその一因だ。
そんな中でも、漁師の斎藤誠也さんはノリ養殖の面白さを感じている。大学を卒業しサラリーマン生活を経て、6年前より桃取町でノリ養殖を始めた。「前の年と同じように作業をしても同じノリにはなりません。難しいけれど面白いです。この仕事は自分がこうしようと考えたことができ、その結果が出るのでやりがいがあります」。始めた当初は3年ぐらい不作が続いたが、清水剛幸(たけゆき)さんら漁師仲間と何とか乗り越えた。自分たちが作ったのりを、ぜひ食べる直前に焼き、焼き立ての香りやパリパリとした食感を楽しんでほしいと言う。
共同加工場で乾燥した板のりはまだ水分を含む。みえぎょれん販売では、仕入れたのりをもう1回乾燥させる「火入れ」を行う。これが77年より取り組んでいる「伊勢のり」だ。その後89年に「焼のり」が登場する。現在市販では、伊勢のりのように焼き加工がされていないのりはほとんど見られない。みえぎょれん販売の前田さんは、「生活クラブは『伊勢のり』の取り組みを続け、あえて手間をかけ焼き立てを食べる、という食文化を今に伝えています」と言う。香り高いのりには、海の恵みと、ノリの養殖にかける生産者の想いが凝縮されている。
ノリの収穫は厳寒期の仕事だ。朝早く船を出しノリを摘む。以前は、漁師が持つ加工場でノリを洗い刻み、枠に流して乾燥させ、板のりに仕上げるまでの全工程を個々に行っていた。その作業は夜中まで続いたという。
鳥羽磯部漁協はこの状況を打開し漁師の作業の軽減を図ろうと、10年前に答志町に共同加工場を設け、収穫したノリの加工を専門の職人に委託するようにした。その後菅島にも設けられ、桃取町でも5年前より稼働が始まった。労働環境改善に一定の成果はあったものの、後継者を増やそうとの目的に反し、最盛期には70軒だった桃取地区のノリ養殖漁師は7軒にまで減ってしまう。船上作業の過酷さは変わらず、気温の変化により不作の年が続いたこともその一因だ。
そんな中でも、漁師の斎藤誠也さんはノリ養殖の面白さを感じている。大学を卒業しサラリーマン生活を経て、6年前より桃取町でノリ養殖を始めた。「前の年と同じように作業をしても同じノリにはなりません。難しいけれど面白いです。この仕事は自分がこうしようと考えたことができ、その結果が出るのでやりがいがあります」。始めた当初は3年ぐらい不作が続いたが、清水剛幸(たけゆき)さんら漁師仲間と何とか乗り越えた。自分たちが作ったのりを、ぜひ食べる直前に焼き、焼き立ての香りやパリパリとした食感を楽しんでほしいと言う。
共同加工場で乾燥した板のりはまだ水分を含む。みえぎょれん販売では、仕入れたのりをもう1回乾燥させる「火入れ」を行う。これが77年より取り組んでいる「伊勢のり」だ。その後89年に「焼のり」が登場する。現在市販では、伊勢のりのように焼き加工がされていないのりはほとんど見られない。みえぎょれん販売の前田さんは、「生活クラブは『伊勢のり』の取り組みを続け、あえて手間をかけ焼き立てを食べる、という食文化を今に伝えています」と言う。香り高いのりには、海の恵みと、ノリの養殖にかける生産者の想いが凝縮されている。

森とつながり、豊かな命を育む海
撮影/田嶋雅已
文/伊澤小枝子
文/伊澤小枝子
『生活と自治』2025年7月号「連載 ものづくり最前線 いま、生産者は」を転載しました。
【2025年7月11日掲載】




